
いざ、色相環を暗記しようと思っても、なかなか覚えられない(涙)
そんなことありませんかー?
そんな方におすすめなのが
色相環を2段階に分けて覚えることです。
前のブログでは12色相環の暗記法について説明しましたので
今回は、残る12色の覚え方を紹介します。
P.C.C.S.色相環とは
色相環とは
色相環というのは、代表的な色相を集めて輪っか状に配置したもの。
色相環にはいくつか種類があって、代表的なのが、マンセル表色系の色相環と、P.C.C.S.の色相環です。
このうち、色彩検定3級で出題されるのがP.C.C.S.の色相環。(2級はマンセル色相環)
P.C.C.Sとうのは、一般社団法人日本色彩研究所が開発したシステムのことで、色を「色相」と「トーン」で考えるのが大きな特徴。色相環は一度覚えてしまうと、ファッションやインテリアの色使いが上達するので、検定試験を利用して覚えておきたいものです。
P.C.C.S色相環の覚え方
P.C.C.S.の色相環は24色で構成されています。
最終目標は、この色相環をマルッと全部覚えること。
とはいえ、なかなかそれは大変な作業です。
そこでおすすめなのが、12色づつ2段階に分けて覚えることです。
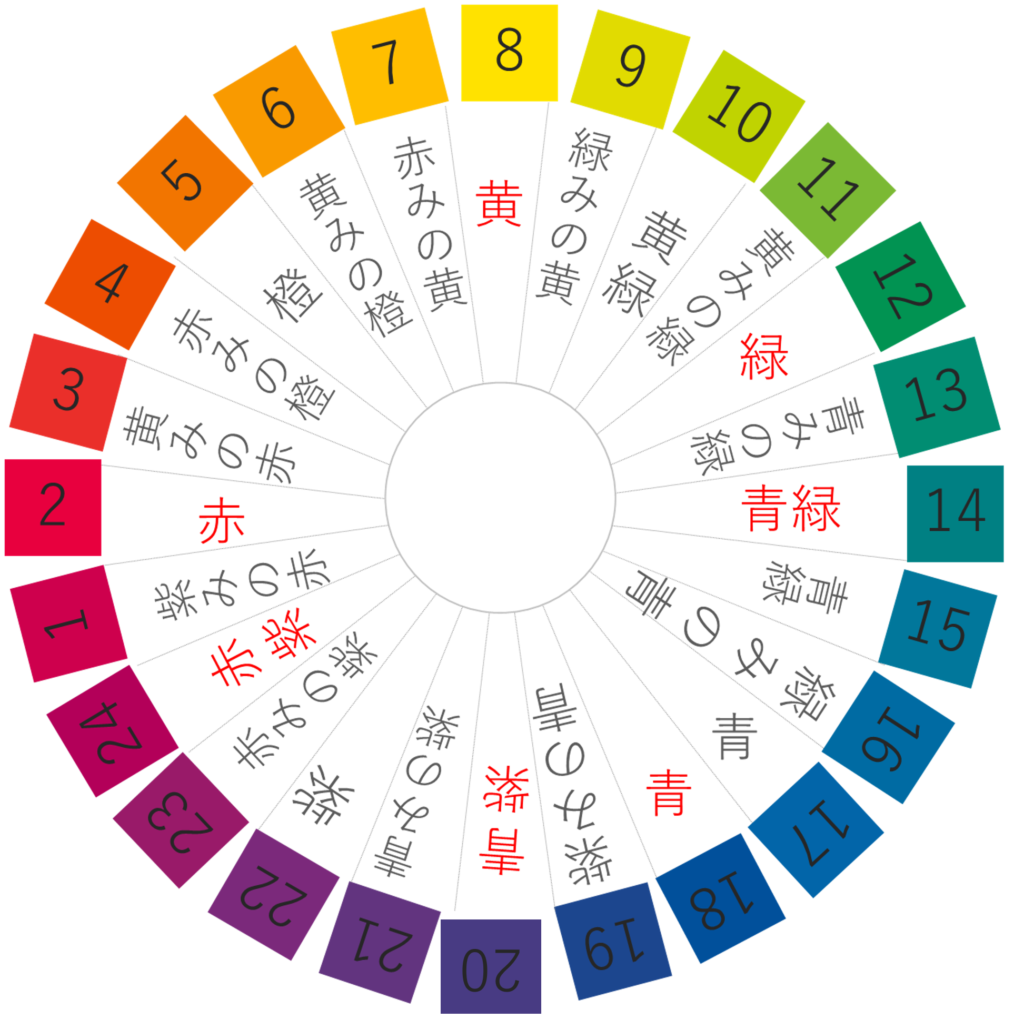
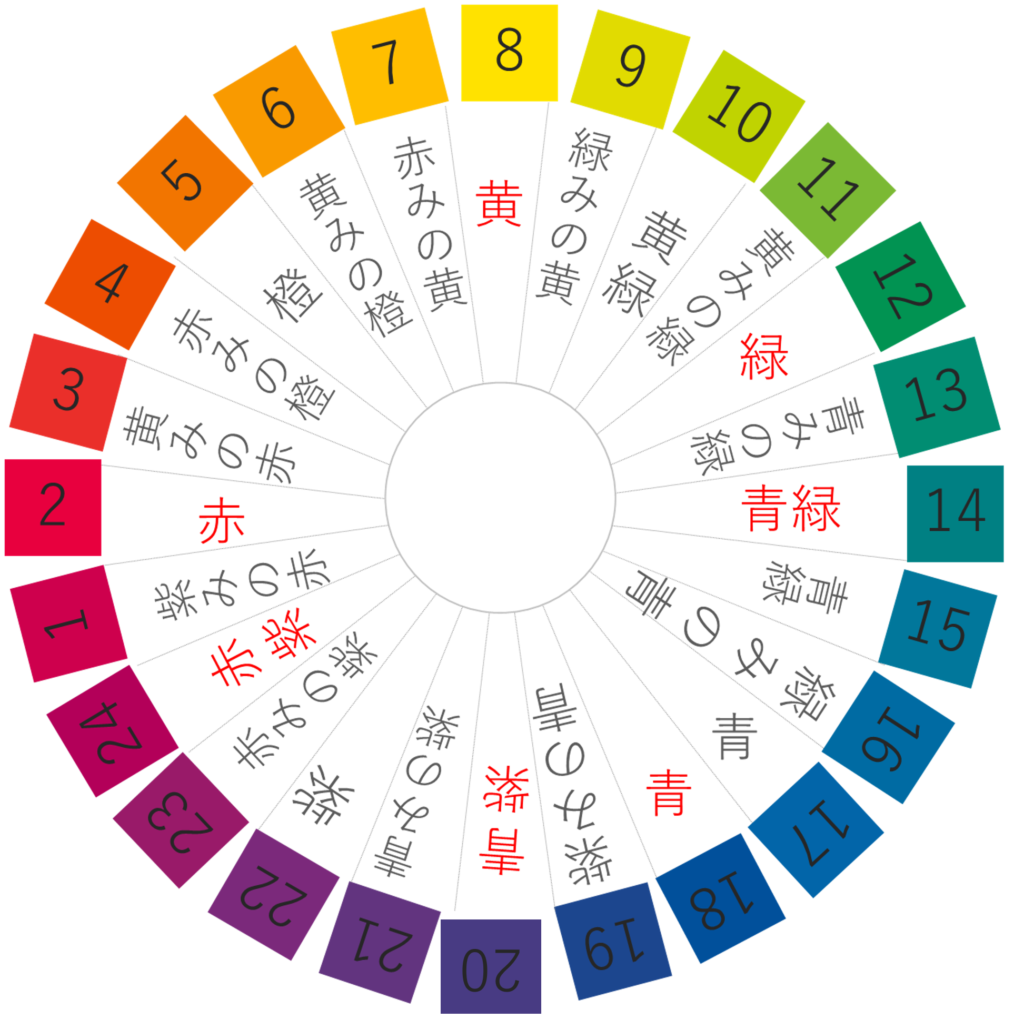




最初は12色の色相環から暗記する
P.C.C.S.の色相環で、日常的によく使われるのが12色の色相環です。
これは色相環の24色のうち、偶数の数字の色だけで構成された色相環。
まずはこの12色の色相環を完璧に覚えることをめざしましょう。
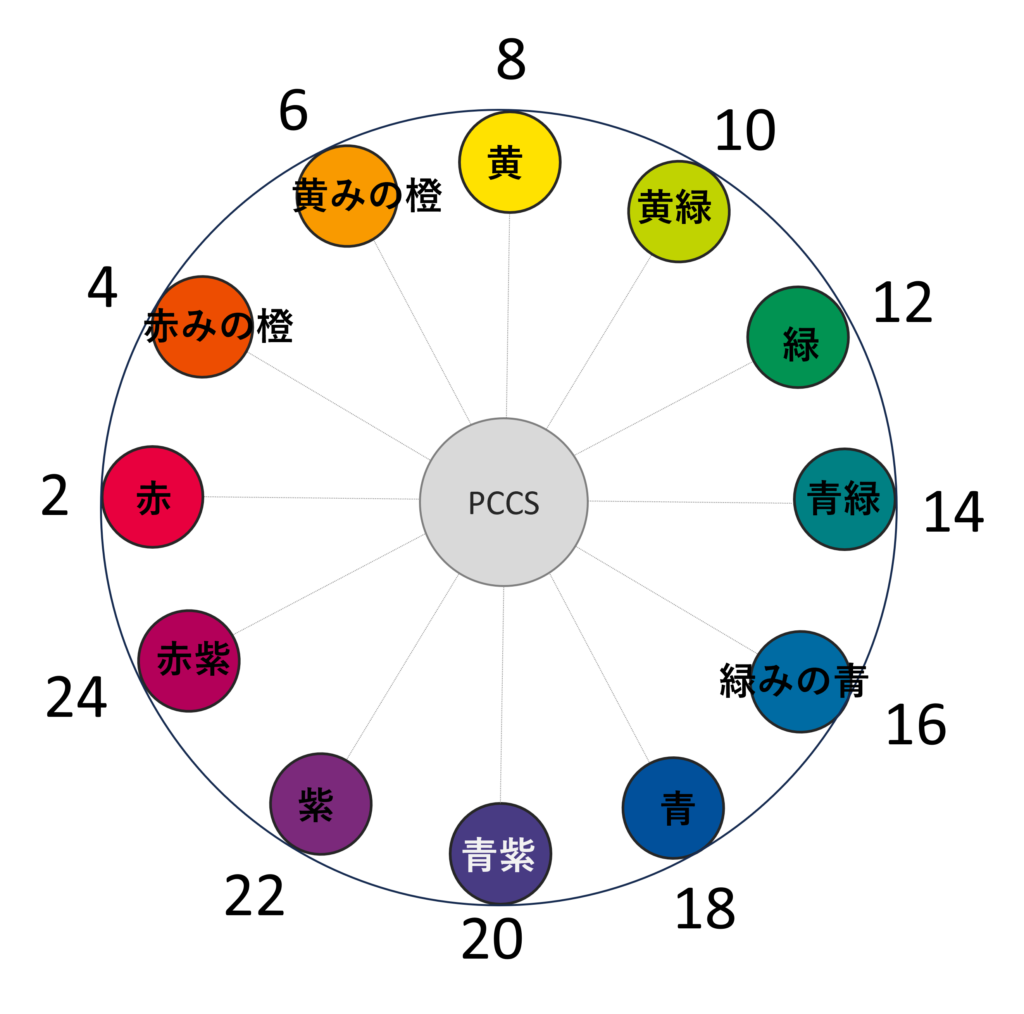
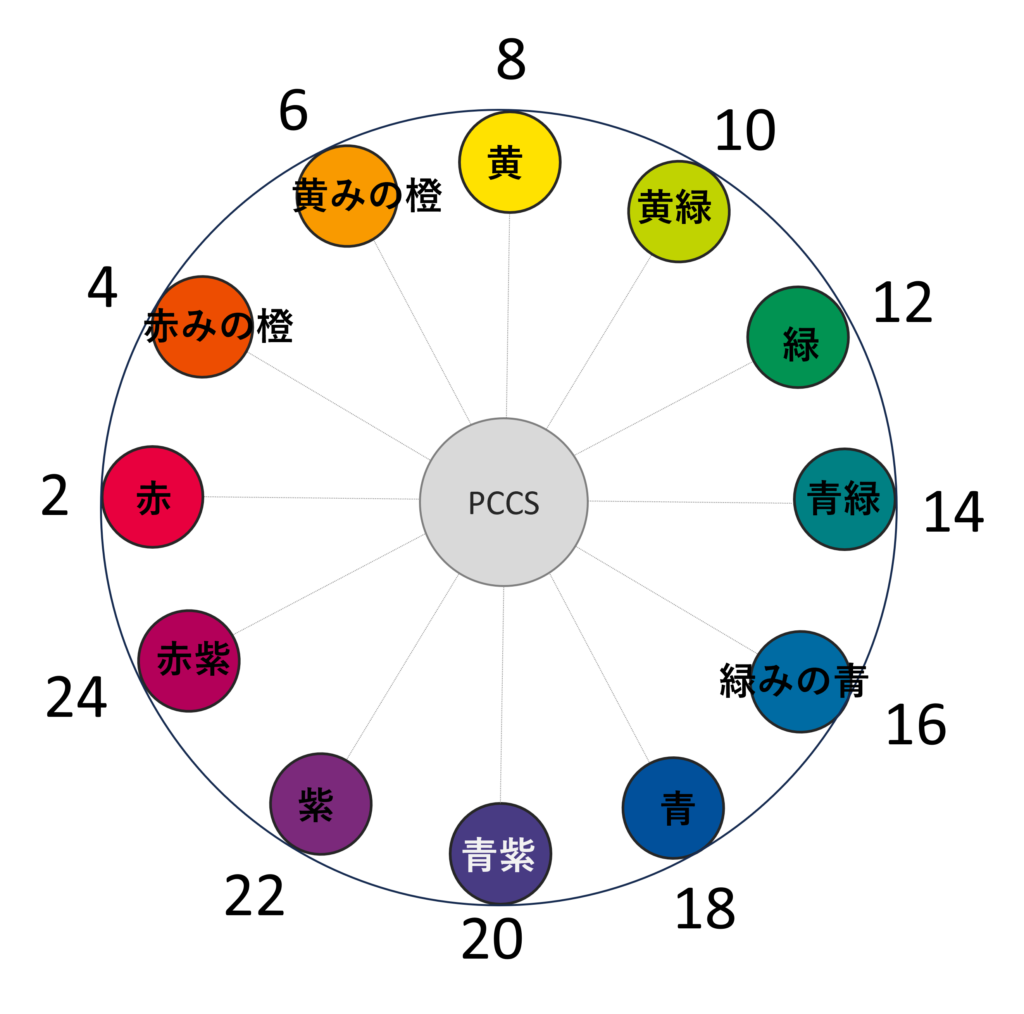


【色彩検定対策】PCCSの色相環を語呂合わせで暗記する方法(その1)
残りの12色の覚え方
①(準備)24色の色相環を用意する


①12色相環を完成させる。
②数字の間に1~23番までの順番に数字をふる
これで24色色相環のもとになる図ができました。
あとはこの〇に奇数番号の色を配置ていきます。


② 色を配置するルール
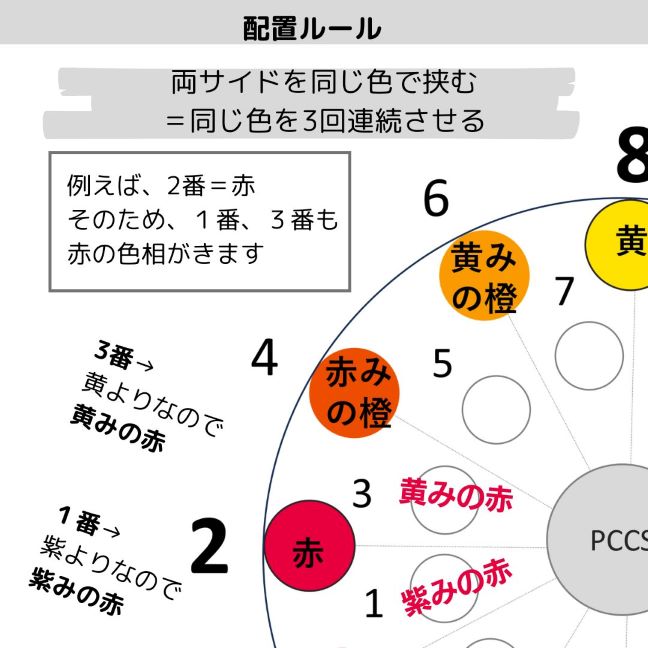
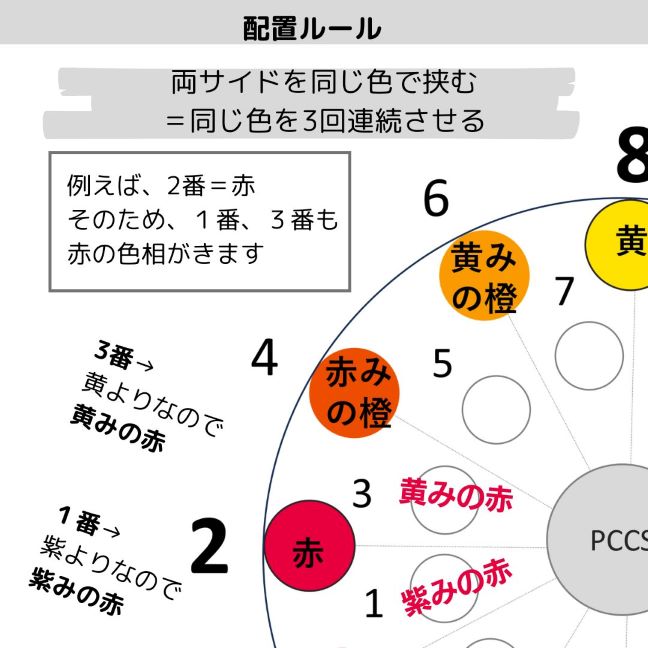
残りの12色を配置するにあたって、
覚えておきたいルールがあります。
それが、
両サイドに同じ色を配置するというルール
言い換えると
同じ色相は3回連続するということです
例えば、12色の色相環で2番の色:赤です。
そのため2番の両サイド、1番、3番も「赤」。
ただし、1番は紫に寄っているので「紫みの赤」
3番は黄に寄っているので「黄みの赤」となるのです。
「〇みの」という風に修飾語になる色は、
基本の5色(赤、黄、緑、青、紫)だけ。それ以外の色、例えば「黄緑み」という様な修飾語は存在しません。修飾語を何にするか迷ったらその色に一番近い「基本の5色」を探しましょう。
③ 実際に色を配置していく


5番の色
「赤みの橙」と「黄みの橙」に挟まれている色なので橙
7番、9番の色
どちらも色相は「黄」。
7番は「赤」に近いので、赤みの黄
9番は緑に近いので、緑みの黄


11番、13番の色
どちらも色相は「緑」。
11番は「黄」に近いので、黄みの緑
13番は「青」に近いので、青みの緑
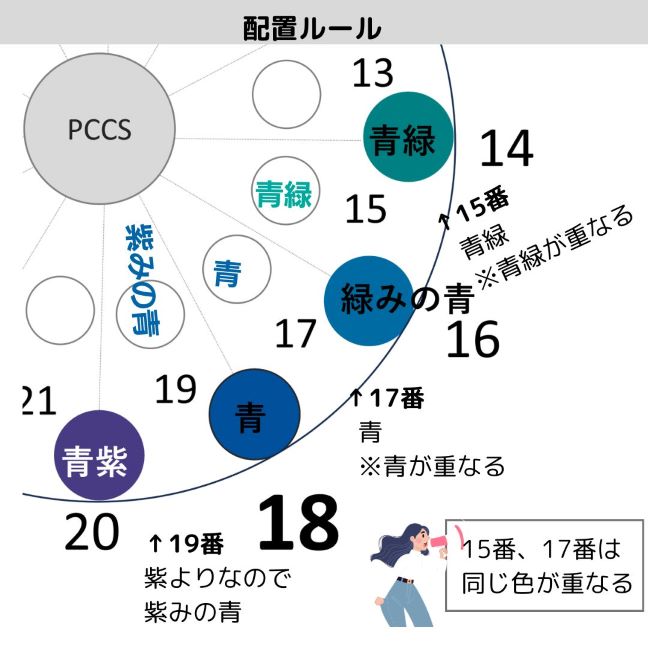
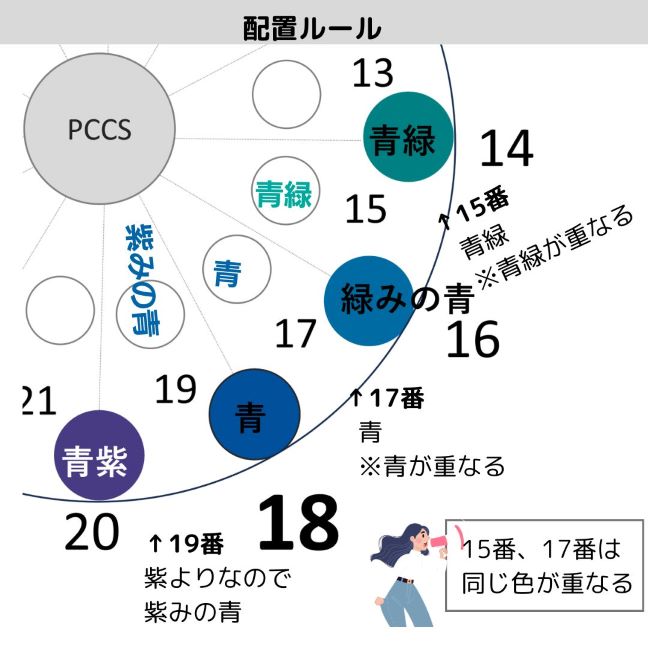
15番、17番の色
イレギュラーなルールになるのが、15、17番。
ここは同じ色が2回繰り返されます。
15番は14番と同じ、青緑
17番は18番と同じ、青
19番の色
色相は「青」。
「紫」に近いので、紫みの青


21番、23番の色
どちらも色相は「紫」
21番は「青」に近いので、青みの紫
23番は「赤」に近いので、赤みの紫
これで1~23番までの配置は完了。
これを12色の色相環と合わせると、24色の色相環が完成します✨


あとは繰り返し書いて覚えるのが、確実です。
当日は、試験が始まったら、まずはこの色相環をどこかに書きだしておきましょう。
それからじっくり試験問題に取りかかると、落ち着いて臨むことができると思います。
色彩検定は色々と覚えることがあって大変ですが、後々の生活の中でも使えるものも多いです。
ぜひコツをつかんで暗記してみてくださいね。


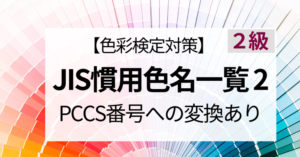
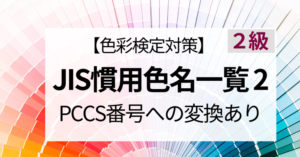

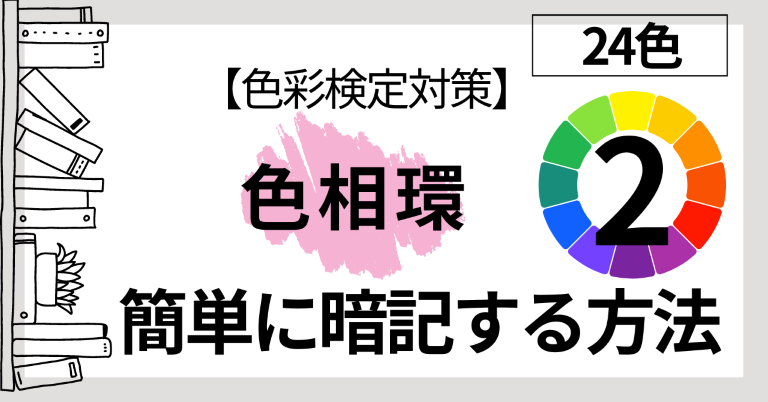


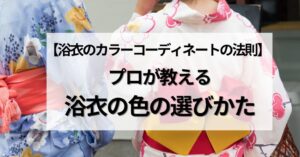

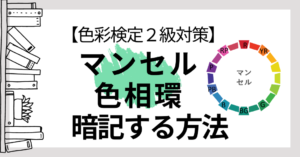


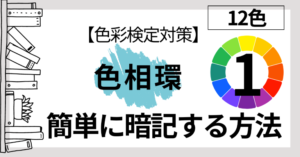
コメント