
「色彩検定には興味があるけど勉強する時間がとれない(涙)」
そんな方も多いですよね。
そこで!ここでは、私が受験した経験も活かして
独学でも合格できた、無駄のない勉強法を紹介します
ここで紹介しているのは、公益社団法人 色彩検定協会が主催する「文部科学省後援 色彩検定」の勉強法。
ブログを読むとこんなことが分かります。
・色彩検定は何級からチャレンジするのがいい?
・独学は可能?
・必要な勉強時間は?
・独学での勉強のコツは?
色彩検定で最初にチャレンジすべき級は?
色彩検定は1~3級ありますが、どの級から受験しても大丈夫です。
でもこの中で、持っていて’はく’がつくのは1級。
ただ、いきなり1級からチャレンジすることも可能ですが、おすすめではないです。
というのも、1級を理解するためには、2級と3級の内容も正確に理解する必要があるからです。
そのことを考慮すると
まずおすすめなのが、3級から受験すること。
あるいは時間的に余裕があれば、2級と3級の併願受験もおすすめです。
色彩検定を勉強する方法
色彩検定を勉強する方法は大きく3つあります
① 通学制のスクール
オンラインの普及によって、色彩検定対策講座を開催するスクールは減少しています。
以前は大手の資格取得スクールでも開講されていましたが、現在は個人のカラーサロンで開催される講座が主流になっています。
② オンラインスクール
現在、主流になっているのが、オンラインスクールです。
都合のよい時間に学べますし、通勤、通学の途中に学ぶことも可能なので、
受講者にとってもメリットのある学び方です。
主なスクールと費用の目安をまとめてみました。
資格の大原 社会人講座
<検定対策講座>
・色彩検定(カラーコーディネーター)(3級コース) /23000円
・色彩検定(カラーコーディネーター)(2級コース) /27000円
・色彩検定(カラーコーディネーター)パックコース(3級コース+2級コース) /46000円
歴史ある大手スクールの検定対策講座。
検定の要点がまとめられたオリジナルテキストがあり効率よく試験対策ができそうです。
ヒューマンアカデミー
<検定対策講座>
パーソナルカラー講座も展開する、カラーやファッションに強いスクールです。色彩検定対策も独自のノウハウがあるため信頼性の高さはピカイチ。オリジナル問題集が用意されているので、様々な回答に対処する力がつくのも強みです
Udemy
<検定対策講座>
・文部科学省後援「色彩検定3級」対策講座/27800円
オンラインスクールの大手Udemyの中の検定対策講座です。
6時間のオンデマンドで、学習時間の制限なしという良心的なシステム。
料金は本来は27800円ですが、現在95%オフで1300円で受講できるようです(2024年5月現在)
③ 独学
色彩検定は独学でも合格は可能です。
私自身も1級を受験した経験があるのですが、最難関と言われる1級でも1次試験は独学で合格できました。
ただし、1級2次はカラーカードを使った実技試験があるため、まったくカードを触ったこともない!という人は
単発の検定対策講座を受けられてもよいのかなと思います。
ここからはその時の経験も踏まえて、独学で効率よく試験勉強する方法をまとめました。
色彩検定3級合格までに必要なこと
1 勉強時間の確保
色彩検定3級合格に必要な勉強時間はだいたい30時間と言われています。
① 試験問題に慣れること
② 覚えるべきことを整理して効率よく暗記すること
3級は”試験問題の慣れ”と”暗気力”が成否のカギを握ります
2 30時間の具体的な勉強方法
① 公式テキストを読む
公式テキストをまずは1通り、ざざっと読みましょう。
理解が難しい所があっても大丈夫。
そこには付箋を貼るなりして印をつけておき、とにかく一度、最後まで読んでみる。
ここでは、どんな項目が書かれているのか?大枠の内容を理解することが目的です
2 過去問題を解く
公式から発売されている「過去問題集」は少なくとも2年分、できれば3年分用意しましょう。
過去問を解いてみると、取り上げられる項目に一定の共通性があること、また使われる図や画像、グラフも同じようなものが使われていることが分かります。
この傾向を読み取って、そこを重点的に理解することがポイントです。
3 暗記ノートをつくる


過去問から読み取れる「毎年出題されるテーマ」を中心に、問題集で間違えたテーマも併せて「暗記ノート」をつくりましょう。
色の知識を暗記するためには、
一度自分の手で書いてみることが効果的です。
綺麗にまとめる必要はありませんが、
頭の中を整理する意味でもノート作成は効果があります。
そして、ノートができたら、あとは
ひたすら、ひたすら、ひたすら(💦)暗記です。
<補足>慣用色名の暗記には
ぜひ下記のページも活用なさってください。
スマホでご覧いただくと移動中に暗記できま
す。時間は効率的に使いましょう!
4 再度テキストを読む
暗記と並行してテキストをもう一度読み返しましょう。
最初の時と比較すると、随分と理解しやすくなっていると思います。
この時、大切だと思うことがあれば、暗記ノートにつけ加えておきましょう。
テキストは、試験までにもう1~2度、トータル3回以上は読み込みましょう。
回数を重ねるごとに理解も深まり、試験への自信にもなってくれます。テキスト大切
5 試験が近づいたら
もう一度、過去問を解きなおしましょう。
ミスする問題は共通していることが多く、そこがご自身にとってのネックです。改めてテキストを見て理解したり、覚えにくい所は重点的に暗記しましょう。
過去問を解くことで、自分の弱点を見つけたり、試験問題に慣れておきましょう
色彩検定のための参考書は必要か?
色彩検定に関しては、公式テキストと公式から出ている問題集があれば、あとは正しく勉強すれば合格できます。そのため、市販されている参考書や問題集は必要ないかと思っています。ただひたすら公式のテキストを読み込むこと、これが合格への近道です。
また色彩検定1級で必要になる配色カードは、2級、3級の受験には必要ではありません。そのため、これらの級の受験では購入する必要はないですが、もし色をしっかり学びたければ購入しておいて損はないと思います。
配色カードは、とてもよくできたツールで、検定試験以外にも色々と活用できます。色は、本やネット画像だけでは理解するのが難しいです。正確な色を見て脳にインプットすることもまた重要です。
どの級を受けられる場合でも、配色カードを合わせて勉強すること、おすすめです。
配色カードとは?どこで買える?センスアップする使い方もあわせて解説
色彩検定VSカラーコーディネーター検定 受験して分かったこと(体験談)
(最後に)独学で勉強して感じたこと
私自身は、独学で色彩検定1級に合格できましたが、これについて思う所があります。
それが、合格のためにと、ただ単に暗記しただけの薄っぺらい知識ってすぐに忘れてしまうということです。
時間をかけて勉強したのに、結局”色をつかいこなせない”という状態は、実は一番もったいないです。
なので、どうせ色の勉強をするのであれば、「色の使いこなし方」までしっかり身に着ける学び方がおすすめです。
色彩検定は独学でも合格可能ですが、色を正しく理解することは一人ではなかなか難しいので、
独学にプラスして、気軽に学べるオンライン講座などを上手に利用していくことが、結局は「色の力をつける」上での近道なのかなと感じています。
時間は有限です。
忙しい大人にとっては、やらないといけないことは試験勉強以外にもいっぱいありますよね。
必要な所に時間を割き、そうでないことは効率化する!
上手に勉強していきましょう。

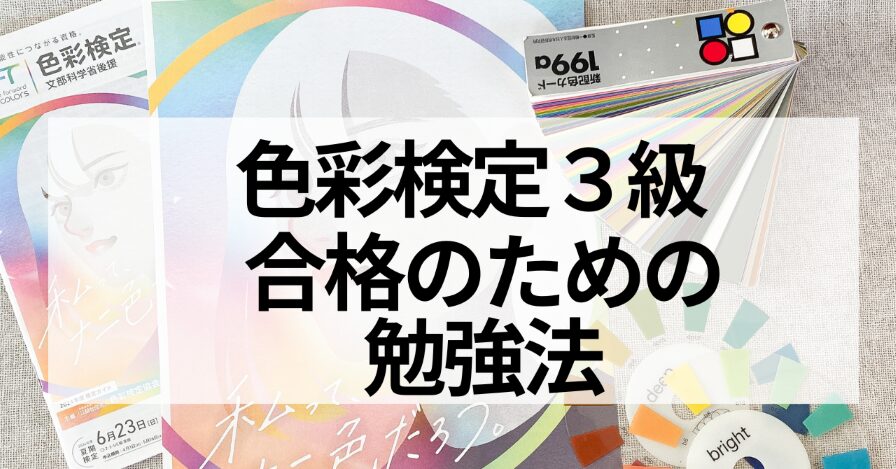






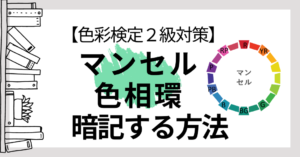


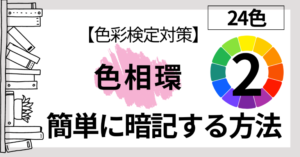
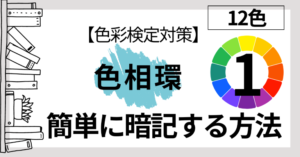
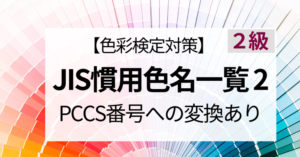
コメント